大学入試 基礎講座 『現代文・小論文の基礎』 其の十九
「接続関係」 〈単純な指示〉
指示語「それ」「これ」は、いわゆる接続詞ではありませんが、前の文との接続関係を示す上で重要な働きをします。
A。「それ」「これ」「そのような」「このような」
…直前の内容「A」を受け、下文に続ける。
指示語は原則、前の内容、それもだいたい直前の内容を受けます(まれに後の内容を指示する場合もありますが)。
直前の内容をそっくりそのまま受けて後の文に接続していきますから、「論=すじみち=一本の糸」を断ち切ることなく、スムーズに展開していくことができます。
受験生の小論文、最初の立論が甘いと一文は長くなる傾向があります。
「あと何書こうかな?」、「とにかく字数かせがなくちゃ」と考えながら書くためです。
何度も言いますが、小論文は考えてから(しっかり立論してから)書くように!考えながら書いてはいけません。
考えながら書くと修飾句、特にも連体修飾句(体言=名詞を修飾する句)が長くなっていきます。
やってみましょうか?
「地球温暖化の原因が二酸化炭素の増加にあるということは科学的に証明されたものではないといって二酸化炭素の排出制限に異を唱える科学者の意見が正しいと証明されることにいったい何の意味があるのだろう」
「科学者」より前がすべて連体修飾になっています。
えてして、主語と述語が対応していなかったりします。書いている本人が「主―述」の対応を見失ってしまうのですね。
句読点をちょっと工夫し、短文に分けて「指示関係」「接続関係」を明示するとかなり読みやすくなります。
「地球温暖化の原因が二酸化炭素の増加にあるということは、科学的に証明されたものではない。それを根拠に二酸化炭素の排出制限に異を唱える科学者の意見もある。しかし、そのような意見が正しいと証明されることにいったい何の意味があるのだろう」
修飾句を長くしない、「主―述」をきちんと対応させる、つまり読者にわかりやすい文章を書くポイントは、短文に分けて「指示関係」「接続関係」を明示することです。
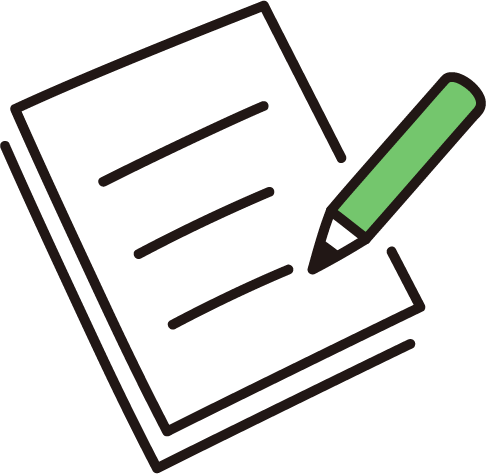
わかりやすい文章の三カ条
一、文は短く、
二、指示語を用い、
三、接続関係を明示する。
当然、短ければいいというものではありません。
優先順位第一位は「中身」でしたね。
また、現代文、古文、漢文の問題でも指示語の内容がよく問われます。
指示内容はだいたい直前にあるはずです。
指示する範囲が広ければ、結局は要約力が問われることになります。
小論文できちんと立論し、正しく指示語、接続詞を用いて論述する、ということは、そっくりそのまま現代文の演習を裏側からやっているにすぎないんですね。

